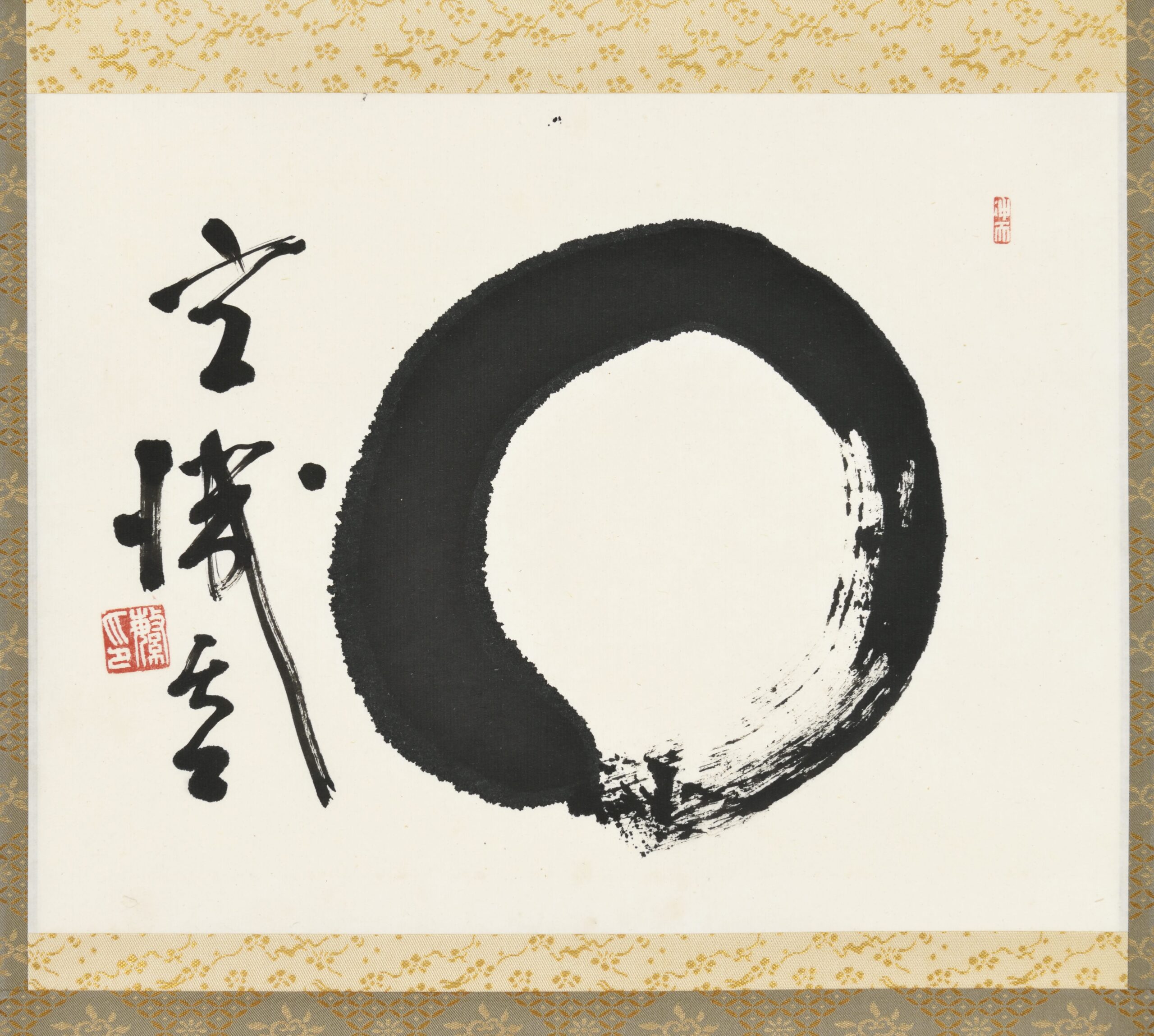
吉田鷹村は、書の伝統と健全を尊び、真に新しい表現世界を求め続けた独往の書家である。また、混迷する昭和・平成の書道界にあって、静かにしかし堂々と、書の王道を貰き、正路を示した孤高の学者、教育者でもある。
門下に集うわれわれは、鷹村卒寿の頃から著述を一所に集め整えておかなければならないという思いを強くするようになった。鷹村が求め到り得た書の源泉に自らも迫りたい、その学芸の道程を自らも辿りたい、学書の道を進む脚力を強くしなければという思いを深めていった。そしてその収集・整理を進める中で、このような幅広く深い学識、豊かな情意の基に省察された書論・書話は、日本の文化として、歴史の中に残すべき大切なものであると確信するに到ったのである。
鷹村白寿の年に出版することを目指して、この選集の編纂は始められた。鷹村もこれを喜び、かかる高齢にしてなお精力的に、原稿の選別や加筆修正を行っていったのであった。
然るに、令和元年の秋、溘焉として旅立ったのである。
広遠な学識、厳しい修行、山野を跋渉することを趣味とし、天地自然と共にあった日常の中から渾然として湧き出で、紡ぎ出された著作の数々は、書の正道を示す標であり、また書道文化の正統の顕示である。劉煕載は「高韻・深情・堅質・浩気」を書の必須要件として挙げ、一を欠けば書とはならないと言ったが、高韻・深情・堅質・浩気がここに集められた一篇一篇にあるいは薫り高く漂い、あるいは厳然として存することを感得されることを思う。
本格の書が引き継がれ、盛んなることを切に願いつつ、『吉田鷹村選集』を刊行する。
令和二年秋
たかむら会
(『吉田鷹村選集』―序に代えて、より)